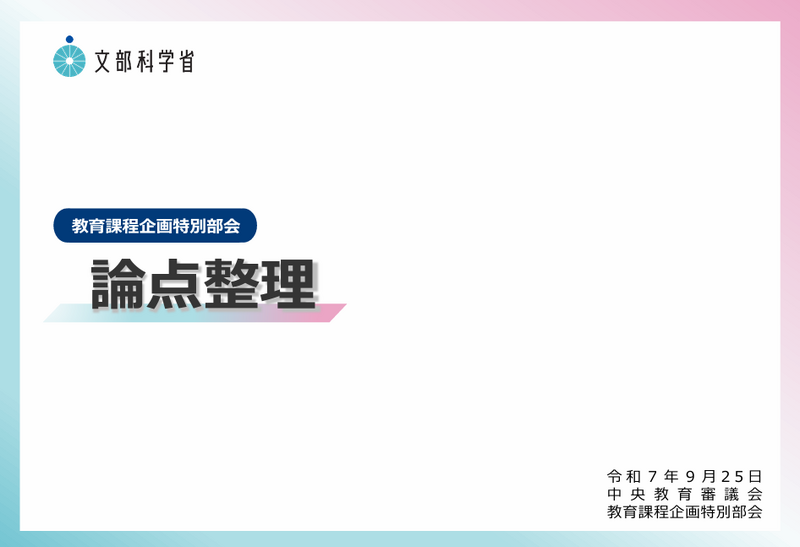文部科学省からの情報
次期学習指導要領に向けた基本的な考え方等を整理した「論点整理」について
【R7.11.25(火)更新】
来月開幕! 東京2025デフリンピック
【R7.10.24(金)更新】
令和7年11月15日~26日までの12日間、東京2025デフリンピックが開催されます。
「デフリンピック」とは、デフ+オリンピックのことであり、デフ(Deaf)とは、英語で「耳が聞こえない」という意味です。
デフリンピックは、国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」であり、日本では初めての開催となります。
文部科学省では、「いよいよ!開催直前デフリンピック予習ガイド」と題して、デフリンピック特有の競技やルール、注目選手などの見どころをまとめた記事を、文部科学省「ミラメク」noteにて公開しています。詳しくは、こちらからご覧ください。
(画像をクリックすると、文部科学省「ミラメク」noteの該当ページ(いよいよ!開幕直前東京2025デフリンピック)へアクセスできます。)
また、スポーツ庁のWebページにおいても、東京2025デフリンピックについて、大会概要や大会エンブレム、マスコットなど、大会に関連した情報が掲載されております。こちらも合わせてご覧ください。
(画像をクリックすると、スポーツ庁の該当ページへアクセスできます。)
〇 関連記事(当センターWebページにて過去に掲載した内容です。クリックすると、該当ページへアクセスできます。)
→ 「NISE特別支援教育リーフの最新号を発行(Vol.27 デフリンピックから学ぶ きこえない・きこえにくい人が安心して楽しめるスポーツの工夫)」
「発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集」について
【R7.6.5(木)更新】
文部科学省は、教育と福祉が連携し、行政分野を超えた切れ目のない一貫した支援を進めていくために、「発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集」を作成し、文部科学省ホームページに掲載しています。
本事例集は、概要版と詳細版の2部構成となっており、概要版はA4見開きサイズで各自治体の取組が簡潔に紹介されています。
また、事例3として、札幌市の取組が掲載されており、「サポートファイルさっぽろ」の作成と個別の教育支援計画としての活用について、連携のポイントや保護者、学校、関係機関それぞれにとっての成果等が紹介されています。
詳しくは、こちら(文部科学省ホームページ)をご覧ください。
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドラインについて
【R7.3.5(水)更新】
文部科学省は、生成AIの概要、基本的な考え方を示した上で、学校現場において押さえておくべきポイントとして、利活用する場面や主体に応じた留意点について、現時点の知見を基に可能な限り具体的に示すなどして、「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」の改訂を行いました。
本ガイドラインの参考資料には、各場面や主体に応じて生成AIを学校現場で利活用する際に押さえておくべきポイントを整理したチェック項目や生成AIパイロット校における先行取組事例、学校現場において活用可能な研修教材等の情報もまとめられています。
一人一人のニーズや特性に合った学びの実現や、新たな視点やより深い視点の出力から学びをより一層深めるなど、今後さらに利活用が進むことが期待されています。
また、北海道教育委員会においても、ICT活用ポータルサイトにおいて、「生成AIの利活用に関するページ」を作成し、各種情報をまとめて発信していますので、併せてご活用ください。
〇 生成AIの利活用に関するガイドラインの詳細は、こちらのWebページ(文部科学省)
〇 生成AIの利活用に関する情報は、こちらのWebページ(道教委ICTポータルサイト)
多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について(諮問)
【R7.2.7(金)更新】
文部科学省は、令和6年12月25日に「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」を中央教育審議会に諮問しました。
本諮問の具体的な審議事項として、第一に「社会の変化や学習指導要領の改訂等も見据えた教職課程の在り方について」、第二に「教師の質を維持・向上させるための採用・研修の在り方について」、第三に「多様な専門性や背景を有する社会人等が教職へ参入しやすくなるような制度の在り方について」の三つが示されています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。