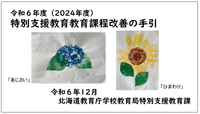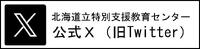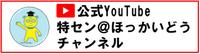新着
【R7.7.11(金)更新】
北海道釧路鶴野支援学校では、聴覚障がい教育部門『オープンスクール』を令和7年7月28日(月)に開催します。
『オープンスクール』では、授業体験や保護者向けの研修会などが行われます。
詳しくは、北海道釧路鶴野支援学校のWebページ(下の画像をクリック)をご覧ください。
【R7.7.11(金)更新】
7日(月)、台湾・基隆市からの視察団が当センターを訪れ、施設見学等を行いました。
今回訪問されたのは、台湾・基隆市教育委員会の職員及び基隆市小学校長など、計24名です。
当日は、相談室や研修室などに、普段実際に行っている教育相談の場面や遠隔による研修支援の環境等を再現することで、参加された皆様に当センターの事業等について理解を深めていただきました。施設の説明や、各事業の概要について紹介した際には、熱心に聞き入る様子が見られ、疑問点を質問する参加者も見られました。
その後、基隆市教育委員会から、センター所員に向けて基隆市の特別支援教育の現状等についてプレゼンテーションによる紹介があり、私たちも海外の特別支援教育について新たな気付きを得たり、理解を深めたりすることができました。
最後に、基隆市教育委員会から当センターに対して、感謝状とプレゼントを頂きました。
頂いた感謝状につきましては、今後館内に展示する予定でおります。当センターにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。
【R7.7.10(木)更新】
今年度、小平高等養護学校では、研究テーマを「『資質・能力の育成を目指した授業づくりの推進』~学びと生徒の未来を繋げる教育活動の充実~」とし、授業づくりに取り組んでいます。
今回は、東北福祉大学 大西 孝志氏をお招きし、教育界の現状や課題について学び、教職員の専門性の向上と校内研究の充実を図るとともに、小平高等養護学校の新教育課程に関わる授業及び説明を全道に向けて広く発信することを目的とし、公開授業研究会を開催します。
参加対象者は、留萌管内の小、中、高等学校の教職員や、全道特別支援学校の教職員で、令和7年10月22日(水)に、北海道小平高等養護学校を会場として集合形式で開催します。
詳細につきましては、小平高等養護学校にお問合わせいただくほか、下記の開催要項等をクリックしてご覧ください。
【R7.7.9(水)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.27 デフリンピックから学ぶ きこえない・きこえにくい人が安心して楽しめるスポーツの工夫
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.7. 8(火)更新】
特別支援学校の教育活動の成果を広く道民に周知することを目的に実施している「特別支援学校ほっこりふれあいプロジェクト」の一環として、札幌視覚支援学校の専攻科生徒4名が来庁し、一人当たり15分程度のマッサージを行いました。
国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」の資格取得に向けた実習の一環で行っているものです。今回からは、簡易ベッドも用意し、背中から腰、足にかけての施術も可能となりました。
実施可能人数に合わせて用意した整理券は、開始すぐになくなってしまうほど、好評をいただいております。 何よりも、施術を受けた方々が「スッキリした、これでこのあとも頑張れそう」「すごく軽くなった、ありがとう」と言って、笑顔で職場に戻って行く姿が印象的でした。
*本プロジェクト「第1回 学習成果発表会」が7月9日(水)に予定されていますので、ぜひお立ち寄りください。
【R7.7.3(木)更新】
国立特別支援教育総合研究所(NISE) では、「令和7年度国立特別支援教育総合研究所 幼児班 夏のセミナー」を令和7年8月20日(水)にZoomによるオンライン配信で開催します。
本セミナーは、幼児班の研究活動の成果を、保育に携わる先生方をはじめ、特別な支援を要する子どもの保育に関心のある皆様に普及することを目的として実施するものです。
詳しくは、下のちらしをクリックして、「国立特別支援教育研究所 幼児班 夏のセミナー」のWebページをご覧ください。
【R7.6.30(月)更新】
国立特別支援教育総合研究所(NISE)では、「令和7年度自閉症・情緒障害特別支援学級担当者専門性向上セミナー」を開催します。
テーマは、自閉症のある子どもの自立活動と各教科等の関連を図った指導についてで、講義やグループ協議等を行います。
また、開催形式は、YouTubeライブ配信やZoomミーティングなどを活用したオンラインでの開催となります。
詳しくは、下記の開催要項や案内チラシをご覧ください。
【R7.6.26(木)更新】
小樽高等支援学校では、生徒指導の基盤を再認識したり、教育課題について様々な方に学びながら解決したりする機会とすることを趣旨として、令和7年7月28日(月)に生徒指導研修会を実施します。
講師は、札幌山の手高等学校ラグビー部総監督であり、北海道ラグビーフットボール協会理事長の佐藤幹夫氏です。
詳細につきましては、下記の開催要項等をクリックしてご覧ください。
【R7.6.23(月)更新】
肢体不自由教育専門性向上セミナーは、肢体に不自由のある児童生徒の指導に携わる教職員が、肢体不自由教育にかかわる基礎・基本を実践的に研修することにより、その基盤づくりを図ることで各人の指導実践力を高めることを目的に開催しています。
今年度、「第20回北海道肢体不自由教育専門性向上セミナー」を、令和7年7月28日(月)、29日(火)に、北海道真駒内養護学校を会場として集合形式で開催します。
この度、セミナーの二次案内が公開されました。詳しくは、下記の案内をクリックしてご覧ください。
【R7.6. 20(金)更新】
室蘭聾学校では、今年度より「苫小牧相談室」を開設しました。
相談室では、「きこえ」と「ことば」の相談を受け付けています。
詳しくは、こちらをご覧いただくか、室蘭聾学校にお問い合わせください。
【R7.6.18(水)更新】
函館養護学校のWebページに、令和7年7月7日(月)に開催される「令和7年度函館養護学校 高等部見学会」の案内が掲載されました。
見学会では、授業見学や校内見学、寄宿舎見学などが行われます。
詳しくは、函館養護学校のWebページからご覧ください。
【R7.6.18(水)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.26 「できること」「やりたいこと」を支える支援機器の活用ーアクセシビリティとアシスティブテクノロジーー
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.6.17(火)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第50号を発行しました。
今号では、道立スクールドライブ(Sドラ)の活用について紹介しています。
また、ICT活用ポータルサイトのリニューアルや各種研修の実施状況について掲載されていますので、併せてご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.6.6(金)更新】
北海道教育委員会は、職業学科や専攻科を設置する道立特別支援学校の教育活動の成果を広く道民に周知することを目的に、「特別支援学校ほっこりふれあいプロジェクト」を実施します。
この度、「特別支援学校ほっこりふれあいプロジェクト」の案内や、取組の様子等をご覧いただけるページを、当センターWebページ内に作成しました。
今後も、学習成果発表会の日程や案内チラシ、当日の取組の様子等について、随時発信していきます。
「特別支援学校ほっこりふれあいプロジェクト」ページはこちらからご覧ください。
【R7.6.5(木)更新】
文部科学省は、教育と福祉が連携し、行政分野を超えた切れ目のない一貫した支援を進めていくために、「発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集」を作成し、文部科学省ホームページに掲載しています。
本事例集は、概要版と詳細版の2部構成となっており、概要版はA4見開きサイズで各自治体の取組が簡潔に紹介されています。
また、事例3として、札幌市の取組が掲載されており、「サポートファイルさっぽろ」の作成と個別の教育支援計画としての活用について、連携のポイントや保護者、学校、関係機関それぞれにとっての成果等が紹介されています。
詳しくは、こちら(文部科学省ホームページ)をご覧ください。
【R7.6.3(火)更新】
国立特別支援教育総合研究所(NISE) 発達障害教育推進センターでは、「令和7年度発達障害教育基礎セミナー」を令和7年7月18日(金)~令和8年1月12日(月・祝)の期間にオンデマンドで配信します。
本セミナーの概要については、以下の通りです。夏季休業中の校内研修等にも活用できる内容となっており、個人・団体いずれでも申込みが可能です。
【概要】■名称:令和7年度 発達障害教育基礎セミナー■配信期間:令和7年7月18日(金)~令和8年1月12日(月・祝)■申込開始:令和7年6月2日(月)開始■テーマ:通常の学級における発達障害のある子どもへの支援と環境づくり■対象:教育関係者■形式:オンデマンド配信■講師:笹森 洋樹 氏(常葉大学 特任教授)■内容:・第Ⅰ部(45分)「個に応じた指導・支援について(仮)」 講義(30分)及び対談(15分)・第Ⅱ部(45分)「校内支援体制について(仮)」 講義(30分)及び対談(15分)■申込方法:下記URLよりお申込みください。 https://forms.office.com/r/81FS2cjNiF
なお、詳しい内容につきましては、こちら(NISE 発達障害教育推進...
【R7.6.2(月)】
肢体不自由教育専門性向上セミナーは、肢体に不自由のある児童生徒の指導に携わる教職員が、肢体不自由教育にかかわる基礎・基本を実践的に研修することにより、その基盤づくりを図ることで各人の指導実践力を高めることを目的に開催しています。
今年度、「第20回北海道肢体不自由教育専門性向上セミナー」を、令和7年7月28日(月)、29日(火)に、北海道真駒内養護学校を会場として集合形式で開催します。
詳しくは、下記の案内をクリックしてご覧ください。
【R7.5.30(金)更新】
北海道肢体不自由教育研究協議会(略称「北肢研」)は、道内の特別支援学校(肢体不自由)の教職員が中心となり、日常の教育実践のより一層の発展、充実を期して設立、運営されている研究会であり、主な事業として、肢体不自由教育の発展と教員の専門性の向上を目指し、研究大会を開催しています。
今年度は、令和7年11月19日(水)~21日(金)に、「第71回全国肢体不自由教育研究協議会 北海道大会」兼「第62回北海道肢体不自由教育研究大会 旭川大会」を参集形式で開催します。
詳しくは、下記チラシをご覧ください。
【R7.5.21(水)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第49号を発行しました。
今号では、学校における授業や校務における生成AIの利活用を通して、ICTを活用した学びの一層の充実を図ることを目的とした「生成AIの利活用に関するプロジェクト」について紹介しています。
また、今年度のICT活用に係る研修や、文部科学省による令和7年度リーディングDXスクール事業の指定校の紹介なども掲載されていますので、併せてご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.5.20(火)更新】
特センでは、令和7年度(2025年度)特別支援学校POWERUPセミナーの申込受付を開始しました。
本研修は、道立特別支援学校の教職員を対象としており、講義や協議を通して全道的な視点で特別支援学校の今日的な課題を捉えるとともに、特別支援教育の推進・充実に向けて資質能力の向上を図ります。
詳しくは、こちらのWebページ(下の画像をクリック)にアクセスし、実施要項及びチラシをご確認ください。
【R7.5.14(水)更新】
筑波大学附属桐が丘特別支援学校では、自立活動の指導に悩む教師を対象に、実態把握や指導計画作成等について研修を行い、自立活動の実践的指導力の向上を目指す「令和7年度 自立活動実践力錬成塾」を開催します。
この講座は、Web会議システムを活用し、ケース児について、実態把握、自立活動の指導目標・指導内容の設定、実践の経過・指導改善及び評価の各演習をオンライン上で行います。また、他の教員の視点を学び、新たな気付きを得ることにつなげられるよう、グループ形式で実施されます。
講座の詳しい内容及び参加申込み等につきましては、筑波大学附属桐が丘特別支援学校のWebページ(https://www.kiri-s.tsukuba.ac.jp/)をご覧ください。
【R7.5.13(火)更新】
関西発達臨床研究所は、「第8回 北海道発達支援セミナー」を、6月7日(土)に旭川、8日(日)に札幌で開催します。
本セミナーは、「~心を支え、心を育み、学びを生み出す発達支援~」をテーマに、様々な発達支援の進め方についての説明や発達に応じた学習活動、教材の紹介等を行います。
なお、参加方法について、現地参加と後日配信の視聴による参加があります。
詳しくは、こちら(関西発達臨床研究所Webページ)をご覧ください。
【R7.5. 9(金)更新】
国立特別支援教育総合研究所は、令和5年度研究成果として、明治図書出版より「事例で学ぶ! 発達障害のある高校生の進路指導ガイド 5つのポイントで分かる指導・支援」を出版しました。
発達障がいのある生徒の社会への円滑な移行を支える進路指導とその過程の中で必要となる連携の進め方についてまとめられており、高校の進路担当の先生をはじめ、特別なニーズのある生徒に関わる全ての方に役立つ内容となっています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R6.5.8(木)更新】
広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構と国立特別支援教育総合研究所では、「第6回広島大学D&I推進機構・国立特別支援教育総合研究所ジョイントセミナー」を開催します。
今回のセミナーは、「共に創るウェルビーイング社会 テクノロジーインクルーシブ」というテーマで、生活や仕事、学びの場で役立つ技術にふれながら、これからのウェルビーイングな社会の実現を目指すためのヒントについて、参加者と一緒に考えます。また、障がいの有無を問わず、暮らしを便利にする技術も紹介されます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.5.2(金)更新】
特センでは、特別支援教育に関する教職員の専門性向上を図る取組を支援するために、いつでもどこからでも視聴できる研修用動画を「特センライブラリ」から配信しています。
各動画は、20分程度で構成されており、4月末現在、43本の研修用動画を公開しています。
◇ 配信している研修用動画の一例
・各障がい種における自立活動の指導
・通常の学級に在籍する特別な教育的支援が必要な児童生徒
・高校段階における障がいの特性の理解
・教育相談の基本について など
4月に新学期がスタートし、児童生徒の実態や学級運営の方向性が見えてくるこの時期に、ぜひご活用ください。
詳細の確認や申込みは、こちらのページからお願いします。
【R7.4.25(金)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第48号を発行しました。
今号では、年度当初に学校等に通知された今年度のICT活用に係る方針や令和6年度末に発出した情報セキュリティ対策基準の改定について紹介しています。
また、生成AIを使用するにあたっての注意点や、国の指定事業である「生成AIパイロット校」の公募についてなども掲載されていますので、併せてご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.4.22(火)更新】
新得高等支援学校のWebページに、令和7年6月12日(木)、13日(金)に開催される「令和7年度 新得高等支援学校学校見学会」の案内が掲載されました。
見学会では、学校概要及び教育活動についての説明や、授業・施設見学などが行われます。
詳しくは、新得高等支援学校のWebページ(下の画像をクリック)からご覧ください。
【R7.4.18(金)更新】
北海道教育委員会は北海道保健福祉部と連携し、発達障がい等のある子どもやその保護者への早期からの教育相談や支援体制の充実を図るため、「発達障がい支援成果普及事業」を実施しており、この度、令和6年度(2024年度)の事業成果を発表資料としてまとめました。
本資料集では、令和6年度の連携推進地域である函館市における、個別の教育支援計画や個別の指導計画の記載事項を整理した「はこだて子どもサポートシート」を活用した実践や、市特別支援教育推進協議会における幼保小の連携・接続に向けた取組などが紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。(ページ中段「特別支援教育関係通知・資料等」に掲載されています。)
【R7.4.17(木)更新】
夕張高等養護学校のWebページに、令和7年6月11日(水)に開催される「令和7年度 北海道夕張高等養護学校 学校説明会」の案内が掲載されました。
説明会はオンライン(Zoom)で開催され、学校概要の説明や質疑応答などが行われます。
詳しくは、夕張高等養護学校のWebページ(下の画像をクリック)から、ご覧ください。
【R7.4.15(火)更新】
特センでは、令和7年度特別支援教育コーディネーター基本研修の申込受付を開始しました。
本研修は、主に特別支援教育コーディネーターの経験年数が概ね1~3年の教員を対象としており、校内支援や教育相談等で必要となる基本的な知識・技能等について学ぶことができます。
詳しくは、こちらのWebページ(下の画像からクリック)にアクセスし、実施要項及びチラシをご確認ください。
【R7.4.11(金)更新】
国立特別支援教育総合研究所では、「自閉症のある子どもの自立活動と各教科等の関連を図った指導を考えよう!」というリーフレットを作成しました。
このリーフレットでは、各教科等での子どもの課題を踏まえた自立活動の時間における指導や、自立活動を踏まえた各教科等の学習での配慮について、事例をもとに紹介されています。
詳しくは、こちらからご覧ください。
【R7.4.9(水)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.25 人工内耳をつけた幼児児童生徒への支援
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.4.11(金)更新】
現在掲載中の「巡回教育相談の案内ちらし」について、【上川南会場】の実施会場の変更がありましたので更新しています。
上川南会場の巡回教育相談をご検討の保護者の方は、改訂版をご確認ください。
※実施日に変更はありません。
変更なし 4月11日改訂版更新 変更なし
【R7.4.1(火)更新】
特センでは、令和7年度特別支援教育基本セミナーの申込受付を開始しました。
本セミナーでは、特別支援教育の基礎・基本、障がいの状態に応じた指導や支援に関する基本的な知識・技能等について学ぶことができます。
詳しくは、こちらのWebページにアクセスし、実施要項及びチラシをご確認ください。
【R7.4.1(火)更新】
特センでは、令和7年度の当センター所長の挨拶文を掲載しました。
令和7年度の主な取組にも触れていますので、是非ご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.3.27(木)更新】
特センでは、令和6年度重点研究の成果として、研究紀要「知的障がい特別支援学校における授業改善に関する研究~文部科学省著作教科書(星本)を活用した児童生徒の資質・能力の育成を目指す授業づくり~」を、当センターWebページに掲載しました。
本研究紀要では、研究協力校との授業づくりを通して文部科学省著作教科書(以下、「星本」という。)を活用した授業モデルを構築するとともに、星本の活用の効果を明らかにすることにより、知的障がいのある児童生徒の資質・能力を育成するための授業づくりに活用いただける内容としています。
本研究紀要を知的障がいのある児童生徒を指導する教職員の専門性の向上及び授業づくりの充実に向けて活用できるものと考えていますので、御一読いただけましたら幸いです。
詳しくは、こちらのページ又は下のサムネイル画像から御覧ください。
クリックして研究紀要のページへ
【R7.3.26(水)更新】
北海道教育委員会では、医療的ケアが必要な児童生徒が通学する道立学校での活用を想定して作成した、「医療的ケアハンドブック」を改訂しました。
医療的ケアが必要な児童生徒が、安全な環境の下、充実した学校生活を送ることのできる体制を整備するためのポイントなどを。3つの分冊で示しています。 また、「道立学校における医療的ケア」保護者向けリーフレットも併せて改訂しております。 詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
(第1編) (第2編) (第3編) (保護者向けリーフレット)
【R7.3.21(金)更新】
特センでは、今年度、石狩市立花川小学校 赤 塚 邦 彦教諭が道教委事業「公立学校教員長期研修制度」により、長期研修者として研修に取り組んでいます。
この度、赤塚教諭の今年度の研修成果を「特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に関する一考察 ~特別支援教育コーディネーターによる通常の学級担任との児童の実態の共通認識プロセスの研究~ 」と題した報告書にまとめ、当センターWebページに掲載しました。
本報告書では、小学校における特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に必要な特別支援教育コーディネーターによる通常の学級担任との児童の実態の共通認識プロセスについて、質的・量的に分析した結果と考察についてまとめたほか、教育現場への示唆などについて記しています。
本報告書に記載の内容については、小学校のみならず、中学校や高等学校においても、特別な教育的支援が必要な児童生徒を二次支援につなげるための教育現場での課題解決の一助となるものと考えていますので、御一読いただけましたら幸いです。
詳しくは、こちらのページ...
【R7.3.19(水)更新】
特センでは、令和7年2月に開催した「令和6年度北海道立特別支援教育センター長期研修者研究成果報告会」並びに「令和6年度特別支援教育研究成果報告会」の内容を、期間限定で公開します。
申込み不要でご覧いただけますので、是非ご覧ください。
下記のURLをクリックするか、チラシの二次元コードよりご覧ください。
【長期研修者報告】特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に関する一考察
【重点研究報告1】知的障がい特別支援学校における授業改善に関する研究
【重点研究報告2】特別支援学校教員スタート・プログラムについて
【R7.3.18(火)更新】
北海道特別支援学校文化連盟から、令和6年度「北海道特別支援学校児童生徒文芸作品集39」が発刊されました。
今回の作品集には、北海道内の特別支援学校71校から、作文、随筆、創作文作品が28点、詩・短歌等が39点、書道14点、絵画・造形作品130点が寄せられています。
いずれの作品においても児童生徒一人一人が体験から学んだこと、作品一つ一つに対する思いが多種多様な表現方法で作品に生かされています。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.3.17(月)更新】
令和7年度(2025年度)の要覧をトップページに掲載しました。
令和7年度特センの紹介や主な事業等が掲載されております。
詳しくは、こちらからダウンロードしてご覧ください。
〇委託契約
・特別支援教育センター庁舎等の清掃業務について
随意契約により締結する契約の内容等.pdf
随意契約結果一覧.pdf
【R7.3.14(金)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育に学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.24 困難さのある高校生の進路指導の充実を目指して~自己理解に焦点を当てて〜
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.3.13(木)更新】
NISEは、特別支援教育を学ぶ方や教育関係者に向けて、「特別支援教育の基礎・基本 第4版」を刊行しました。
特別支援教育に関する最新の理論、制度の変遷のほか、障がいのある子どもの実態把握、指導法等、特別支援教育に関する知っておきたい知識を一冊にまとめられています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.3.11(火)更新】
北海道教育委員会は、広く北海道教育委員会所管の行政事項の概要を紹介することを目的として、教育便覧を発行しました。
主に、次の情報が掲載されています。
・北海道管内別面積・市町村数
・北海道教育の基本理念、北海道教育推進計画
・令和6年度教育行政執行方針、主な事業
・教育委員会予算
・公立学校数・学級数・児童生徒数、職員定数一覧、本務教員数一覧
・小・中学校の概況
・高等学校等の概況
・特別支援学校の概況 など
ほかにも、特別支援学級数・児童生徒数や特別支援学校一覧など、特別支援教育に関する情報も掲載されています。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.3.5(水)更新】
文部科学省は、生成AIの概要、基本的な考え方を示した上で、学校現場において押さえておくべきポイントとして、利活用する場面や主体に応じた留意点について、現時点の知見を基に可能な限り具体的に示すなどして、「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」の改訂を行いました。
本ガイドラインの参考資料には、各場面や主体に応じて生成AIを学校現場で利活用する際に押さえておくべきポイントを整理したチェック項目や生成AIパイロット校における先行取組事例、学校現場において活用可能な研修教材等の情報もまとめられています。
一人一人のニーズや特性に合った学びの実現や、新たな視点やより深い視点の出力から学びをより一層深めるなど、今後さらに利活用が進むことが期待されています。
また、北海道教育委員会においても、ICT活用ポータルサイトにおいて、「生成AIの利活用に関するページ」を作成し、各種情報をまとめて発信していますので、併せてご活用ください。
〇 生成AIの利活用に関するガイドラインの詳細は、こちらのWebページ(文部科学省)
〇 生成AIの利活用に関する...
【R7.2.28(金)更新】
独立行政法人教職員支援機構は、校内研修シリーズNo.171として「合理的配慮の提供と特別支援教育に関する校内支援体制の充実について」を掲載しました。
本動画では、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課の加藤 典子 特別支援教育調査官の講義を視聴できます。
主に、次の内容から構成されています。
1 共生社会の実現のために
2 インクルーシブ教育システムの実現
3 合理的配慮の提供
4 校内委員会の機能強化
5 まとめ
インクルーシブ教育システムの実現や合理的配慮の提供に関する理解を深めるため、自主研修や校内研修などにご活用ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.2.26(水)再掲】 特センでは、「特別支援教育ほっかいどう」第30号(通巻第74号)を発行しました。 本号では、「本道の特別支援教育における取組の充実に向けて」を特集し、通級による指導の充実、医療的ケアの充実に向けた取組及び特セン事業の紹介を掲載しています。 特別支援教育の充実に向け、学校や地域において取組を推進する上で参考となる内容ですので、ぜひご覧ください。
こちらのWebページから、ご覧ください。
【R7.2.25(火)更新】
北海道教育委員会では、北海道の学校教育や社会教育、生涯学習、文化に関する情報など、様々な情報を広報してきましたが、「皆さんにもっと情報を届けたい!」という思いから、noteにおいても情報発信しています。
道立の特別支援学校においても、noteページを開設し、学校紹介や日々の教育活動の様子を発信しています。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
https://hokkaidopref-edu.note.jp/
【R7.2.19(水)更新】
NITS(独立行政法人教職員支援機構)では、学校で実施する校内研修で使用できる講義動画を提供しています。
校内研修の始めに視聴し、それをふまえた演習・発表を行うことで、校内研修の更なる充実を図り、教員の資質能力の向上を目指すことができます。
今年に入ってからも、多くの動画が新たに掲載されていますので、その一部を紹介します。
・いじめのとらえ方と予防Ⅱ
・学校の教育目標を具現化するカリキュラム・マネジメント
・これからの学校におけるミドルリーダーシップ
・コーチングのスキルと活用Ⅰ
・発達の段階に応じた道徳科の指導 など
各動画の視聴は、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.2.17(月)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育について学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.22 知的障害特別支援学級における教育課程編成と授業づくり
Vol.23 ダウン症のある子供の理解と支援~より深く知って、日々の実践に生かしてみよう!~
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【R7.2.14(金)更新】
東京大学先端科学技術研究センター個別最適な学び寄附研究部門「LEARN」では、教育現場の課題に対応するため、教員研修をオンラインで効率的に実施できるプログラム「LTA(LEARN Teachers Academy)」を開発し、無償提供しています。
この度、本プログラムの活用に係り、教育委員会、教育センター、教員研修担当者向けのセミナーを実施します。
本セミナーでは、教育現場の課題解決に直結する動画コンテンツの紹介や効率的かつ実践的な教員研修の設計に係る事例などの紹介があります。
日時:2025年3月4日(火)15:00-16:30
方法:東京大学へ参集か、オンラインによる配信
詳細の確認や申込みは、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.2.12(水)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第46号を発行しました。
今号では、道教委が作成した「道立学校における生成AI利活用ガイドブック」について紹介しています。
「令和6年度(2024年度)ICTを活用した学びのDX事業 ICT活用全道協議会」の部会別協議における各部会講師の研修動画も公開していますので、併せてご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.2.7(金)更新】
文部科学省は、令和6年12月25日に「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」を中央教育審議会に諮問しました。
本諮問の具体的な審議事項として、第一に「社会の変化や学習指導要領の改訂等も見据えた教職課程の在り方について」、第二に「教師の質を維持・向上させるための採用・研修の在り方について」、第三に「多様な専門性や背景を有する社会人等が教職へ参入しやすくなるような制度の在り方について」の三つが示されています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.2.5(水)更新】
文部科学省は、令和6年12月25日に「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」を中央教育審議会に諮問しました。
本諮問の具体的な審議事項の中には、特別支援教育の充実に係る内容が示されております。
例えば、「多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方について」や「これからの時代に育成すべき資質・能力を踏まえた、各教科等やその目標・内容の在り方について」の中で「インクルーシブ教育システムの充実に向け、合理的配慮の提供を含め、障害のある子供たち一人一人の教育的ニーズに応じた、質の高い特別支援教育の在り方をどのように考えるか。その際、特別支援学級や通級による指導に係る特別の教育課程の質の向上、自立活動の充実や小中高等学校に準じた特別支援学校での改善方策をどのように考えるか。」などということも示されています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.2.3(月)更新】
東京大学先端科学技術センターでは、教員・教育学部学生及び教育関係者向けの研修プログラムを構築し、講義動画を公開しています。
本プログラムに登録すると、基礎コースではオンデマンドで、無料で何度でも動画を視聴することが可能です。
教育の本質に関わる基礎知識から新しい教育やICTの動向まで多様な内容を取りそろえていますので、自主研修にお役立てください。
<動画一覧>
・小中学校の先生に役立つ支援技術の基礎と活用
~学びにくさのある子達がスタートラインに立つために~
・障害を理解する
・日常生活から子どものつまずきを考える
・心理検査の効用と限界 など多数
申込みや詳細の確認は、こちらのWebページからご覧ください。
【自主研修のススメ シリーズ】
・NITS研修動画 こちら
・NISE学びラボ こちら
・公開講義の事後配信 こちら
・授業におけるICT活用 こちら
・特センに来所して行う研修 こちら
・特センライブラリ こちら
【R7.1.31(金)更新】 特センでは、「特別支援教育ほっかいどう」第30号(通巻第74号)を発刊しました。 本号では、「本道の特別支援教育における取組の充実に向けて」を特集し、通級による指導の充実、医療的ケアの充実に向けた取組及び特セン事業の紹介を掲載しています。 特別支援教育の充実に向け、学校や地域において取組を推進する上で参考となる内容ですので、ぜひご覧ください。
こちらのWebページから、ご覧ください。
【R7.1.30(木)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第45号を発行しました。
今号では、全道から約350名の方が参加した「令和6年度(2024年度)ICTを活用した学びのDX事業 ICT活用全道協議会」について紹介しています。
文部科学省学校DX戦略アドバイザーの佐藤 和紀准教授による講演の概要や部会別協議、座談会の様子も掲載しています。
ほかにも、個人での研修や校内研修等で活用できる動画の紹介も掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.1.29(水)更新】
道教委は、北海道教育の基本理念、北海道教育委員会のしくみ、道内公立学校の概要を見やすいグラフ等で紹介する「ほっかいどうの教育2024」を発行しました。
道内の特別支援学校の学校数、児童生徒数及び教員数など、各種情報がまとめて掲載されています。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
【R7.1.27(月)更新】
特センでは、学校の給食場面における摂食指導の視点についてまとめた、『安心・安全な給食指導のための「摂食指導」追補版』のリーフレットを作成しました。
発達に偏りのある児童生徒への「給食指導」において必要となる、実態把握の観点などが整理されています。
詳しくは、こちらからご覧ください。
〇 安心・安全な給食指導のための「摂食指導」追補版
【R7.1.22(水)再掲】
特センには、道教委事業「公立学校教員長期研修制度」により、長期研修者として研修に取り組んでいる教諭がいます。
本報告会では、特別支援教育コーディネーターが通常の学級担任とどのように連携し、実態把握の共通理解を図るかを視点に、長期研修者が調査研究してきた取組の成果を報告します。
日 時:令和7年2月14日(金)15:20-16:40
報 告:特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に関する一考察
石狩市立花川小学校教諭 赤 塚 邦 彦
対 象:特別支援教育に携わる教職員
*主に、小・中学校及び高等学校の特別支援教育コーディネーター、特別な教育的支援が必要な児童の指導や支援に携わっている教員及び管理職 等
申込み:こちらのWebページから、各自でお申し込みください。
詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
【R7.1.22(水)再掲】
特センでは、特別支援学校における今日的な課題解決に資するための実践的な研究を行っています。
本報告会では、知的障がい教育における授業改善や経験の浅い教員の育成といった、今日的な教育課題に関する研究の成果を報告します。
日 時:令和7年2月28日(金)15:20-16:40
報告1:知的障がい特別支援学校における授業改善に関する研究について
知的障がい教育室研究員 小 幡 史 門
報告2:特別支援学校教員スタート・プログラムについて
自閉症・情緒障がい教育室研究員 山 口 智 也
対 象:特別支援教育に携わる教職員
主に、特別支援学校教員、小・中学校において知的障がい特別支援学級を担当している教員及び管理職 等
申込み:こちらのWebページから、各自でお申し込みください。
詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
【R7.1.21(火)更新】
国立特別支援教育総合研究所では「とくそうけんキッズルーム」という動画コンテンツを公開しています。
とくそうけんキッズルームには、「みんな友達!知ろう、学ぼう、考えよう」と題した、子ども向けに作成された障がいの理解啓発に関わる動画コンテンツが掲載されています。
詳しくは、こちらからご覧ください。
【R6.1.20(月)更新】
高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用に取り組む企業事例を中心に、身近な障害者雇用の情報を取り上げた月刊誌「働く広場」を発行しています。
成人期を迎えた障害者の働き方や、障害者雇用を進める先進的な取組のヒントのほか、特別支援学校卒業生の活躍の様子などが掲載されています。
教育現場と就労をつなぐために紹介します。
〇 高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebページはこちら
〇 12月号のダウンロードは、こちらのWebページから
※1月号も発行されていますので併せてご覧ください。
【R7.1.17(金)更新】
障害者職業総合センターでは、就労を希望する障がい者のストレングス(長所)や成長可能性、課題等を適切に理解し、就職に向けた必要な支援や配慮を検討するためのアセスメントシートを提供しています。
就労を希望する障がいのある方であれば、障がいの種類を問わず使用が可能であり、個別面談場面を通じて本人が「自分の特徴を理解」したり、「自信が向上」したり、「働くイメージが持てる」などの効果が期待できます。
*教育現場と就労とをつなぐために紹介します。
〇 障害者職業総合センターのWebページはこちら
〇 アセスメントシートダウンロードは、こちらのWebページから
【R7.1.16(木)更新】
全国特別支援学校文化連盟では、毎年、全国の特別支援学校に在籍する児童生徒の作品を集めて、Webページ上で作品展を行っています。
この度、第30回全国特別支援学校文化祭における優秀作品が、全国特別支援学校長会のWebページに掲載されました。
児童生徒のみなさんが一生懸命作った作品がたくさん掲載されていますので、是非、その素晴らしさを楽しんでください。
本道の特別支援学校に通う児童生徒の作品も、複数掲載されています。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R7.1.9(木)更新】
全国障害者雇用事業所協会(以下、全障協)北海道ブロックでは、「広げよう障害者雇用、連携から協働へ!~企業と支援者のネットワークを高めて~」をテーマに、次のとおり障害者雇用セミナーを開催します。
日 時:令和7年2月14日(金)13:30~16:30
形 式:オンラインセミナー
当日は、多くの企業に向けて、障害者就労移行支援、定着支援を行っている就労移行支援事業所の立場から、障がいのある方々が企業で働き続けることができるよう取り組んでいる先進的な支援内容についての講演や就労移行支援事業所との協働による雇用の拡大と定着についての紹介などがあります。
このセミナーは、厚生労働省の委託を受けて、障害者の雇用を検討されている企業関係者等を対象に開催するもので、どなたでも無料で参加いただけます。
詳しい内容及び参加申込み方法は、次のチラシをご覧ください。
〇 セミナーちらしのダウンロード
〇 公益社団法人全国障害者雇用事業所協会のWebページ
【R7.1.8(水)更新】
徳島県教育委員会では、「新時代『発達障がい教育』推進プロジェクトチーム」を中心とした研究者の方々と協働して取り組んだ実践研究の成果を、対面・オンラインやポスターで報告します。
明日から指導実践に活かせる内容が盛りだくさんとなっております。
〇 申込みは、こちらのWebページから
〇 チラシのダウンロードは、こちらから
【R7.1.7(火)更新】
特センでは、特別支援学校における今日的な課題解決に資するための実践的な研究を行っています。
本報告会では、知的障がい教育における授業改善や経験の浅い教員の育成といった、今日的な教育課題に関する研究の成果を報告します。
日 時:令和7年2月28日(金)15:20-16:40
報告1:知的障がい特別支援学校における授業改善に関する研究について
知的障がい教育室研究員 小 幡 史 門
報告2:特別支援学校教員スタート・プログラムについて
自閉症・情緒障がい教育室研究員 山 口 智 也
対 象:特別支援教育に携わる教職員
主に、特別支援学校教員、小・中学校において知的障がい特別支援学級を担当している教員及び管理職 等
申込み:こちらのWebページから、各自でお申し込みください。
詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
【R7.1.7(火)更新】
特センには、道教委事業「公立学校教員長期研修制度」により、長期研修者として研修に取り組んでいる教諭がいます。
本報告会では、特別支援教育コーディネーターが通常の学級担任とどのように連携し、実態把握の共通理解を図るかを視点に、長期研修者が調査研究してきた取組の成果を報告します。
日 時:令和7年2月14日(金)15:20-16:40
報 告:特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に関する一考察
石狩市立花川小学校教諭 赤 塚 邦 彦
対 象:特別支援教育に携わる教職員
*主に、小・中学校及び高等学校の特別支援教育コーディネーター、特別な教育的支援が必要な児童の指導や支援に携わっている教員及び管理職 等
申込み:こちらのWebページから、各自でお申し込みください。
詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
【R7.1.6(月)更新】
北海道教育委員会は、「令和6年度(2024年度)特別支援教育教育課程改善の手引」を作成しました。
本手引では、第1章で「資質・能力の3つの柱」と「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」に加え、「自立活動の指導」との関係性について整理し、第2章では、障がい種ごとの事例が掲載されています。
第2章の事例7~12には、特別支援学級と通級による指導の事例が掲載されています。
資料は、こちらからご覧ください。
【R6.12.26(木)更新】
特センでは、特別支援教育に関する教職員の専門性の向上を図る取組を支援するために、いつでもどこからでも視聴できる研修用動画を「特センライブラリ」から配信しています。
各動画は、20分程度で構成されており、12月現在、43本の研修用動画を公開しています。
◇ 配信している研修用動画の一例
・特別支援教育の現状と課題
・各障がいの理解と関わり方について
・通常の学級に在籍する特別な教育的支援が必要な児童生徒への指導
・心理検査について など
詳細の確認や申込みは、こちらのページからお願いします。
【自主研修のススメ シリーズ】
・NITS研修動画 こちら
・NISE学びラボ こちら
・公開講義の事後配信 こちら
・授業におけるICT活用 こちら
・特センに来所して行う研修 こちら
冬季休業中の自主研修などに、ご活用ください。
【R6.12.25(水)更新】
国立特別支援教育総合研究所では、障害のある児童生徒等の教育に携わる教職員の資質能力向上を図る主体的な取組を支援するため、インターネットによる講義配信「NISE学びラボ」~特別支援教育eラーニング~を行っています。
パソコンやタブレット端末、スマートフォンなど、多様な利用環境で視聴することができます。
また、おおよそ15分から30分程度の講義を通して、いつでもどこでも特別支援教育について学ぶことができます。
約170の講義コンテンツや、複数の講義コンテンツを組み合わせた研修プログラムから、ご自身のニーズに応じた学習ができますので、特別支援教育について理解を深めるためにお役立てください。
詳細の確認や申込みは、こちらのWebページをご覧ください。
【自主研修のススメ シリーズ】
・NITS研修動画 こちら
・公開講義の事後配信 こちら
・授業におけるICT活用 こちら
・特センに来所して行う研修 こちら
冬季休業中の自主研修などに、ご活用ください。
【R6.12.24(火)更新】
北海道教育委員会では、「北海道教育の日」関連事業として児童生徒や教職員から見た学校、学級や児童生徒などにかかわるキラリと光る話題を募集しました。
小樽高等支援学校生徒会執行部の「OKSスマイルプロジェクト始動!」が、特にキラリと光る話題として表彰されました。
詳しくは、こちらのページからご覧ください。
道教委では、noteによる記事掲載も始めましたので、併せてご覧ください。
【R6.12.23(月)更新】
2024年度「高大連携におけるシンポジウム」実行委員会では、「進学重視校におけるこれからの特別支援教育を考える~高大連携に求められること~」をテーマに、高大連携におけるシンポジウムを開催します。
日 時:2025年2月22日(土)13:00~17:30
場 所:北海商科大学2号館5階多目的ホール
対 象:小学校、中学校、高等学校、高等教育機関教職員
参加費:無料
後 援:北海道教育委員会
申込み:こちらのWebページから
チラシのダウンロードは、こちら
*本チラシは、北海道高等聾学校専攻科の学生が作成しました。
【R6.12.20(金)更新】
北海道教育委員会は、「令和6年度(2024年度)特別支援教育教育課程改善の手引」を作成しました。
本手引では第1章で「資質・能力の3つの柱」と「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」に加え、「自立活動の指導」との関係性について整理し、第2章では、障がい種ごとの事例が掲載されています。
第2章の事例1~6には、特別支援学校の事例が掲載されています。
資料は、こちらからご覧ください。
【R6.12.18(水)更新】
独立行政法人教職員支援機構では、全国の学校教育関係職員に豊富で質の高い研修機会を提供するため、いつでもどこでも研修が可能となるよう「校内研修シリーズ」を始め、講義動画などの研修教材を提供しています。
〇 個人や組織でテーマに沿って学ぶ:校内研修シリーズ
〇 学習指導要領について理解する:新学習指導要領シリーズ
〇 校内研修の充実を図る:研修プランシリーズ
〇 授業等の実践に役立てる:実践力向上シリーズ
〇 教師の魅力や学校の様子を知る:基礎的研修シリーズ
〇 教職員研修の在り方を問い直す:シリーズ「これまでの研修、これからの研修」
「校内研修シリーズ」には「特別支援教育の実際〜通常学級における『特別な配慮』〜」や「自閉症スペクトラム当事者からみた特別支援教育」、「特別支援教育総論 学習のユニバーサルデザイン・段階的対応・合理的配慮」など、特別支援教育の理解を深めるための内容も多数提供されています。
詳しくは、こちらのWebページからご覧ください。
【自主研修のススメ シリーズ】
・公開講義の事後配信 こちら
・授業におけるICT...
【R6.12.17(火)更新】
北海道特別支援教育学会道央支部では、先に実施した強度行動障がいに関する研修会における講話を、先生方の実践に生かしていただくため、オンデマンドで一般公開します。
次のWebページから、研修用動画をご覧ください。
令和7年1月31日までの限定公開となっておりますので、冬季休業中の自主研修などにお役立てください。
視聴できる動画は、次のとおりです。
【R6.12.16(月)更新】
特センでは、摂食指導に関する基本的な考え方や対応等についての要点をまとめて、令和2年に作成したリーフレット「安心・安全な給食指導のための『摂食指導』」を、改訂しました。
北海道肢体不自由教育摂食実技研修会における講義や実技指導の内容を踏まえて、「早すぎる自食指導について」を追加するなど、内容を見直しましたので、日々の給食指導場面の参考としてご活用ください。
リーフレットは、こちらからダウンロードしてご覧ください。
【R6.12.11(水)更新】
特センでは、授業におけるICT活用の専門性を高め、自身や自校の取組の充実に生かすことを目的に、「特別支援学校の授業におけるICT活用」をテーマに研修用動画を配信します。
本配信研修では、障がい種ごとに、ICTを積極的に活用されている先生方の実践事例を公開します。
※ 本研修動画は教職員等の教育関係者のみを対象に、動画の視聴と講義資料の閲覧ができるようにしております。
詳細は、各学校等へ送付した事務連絡とチラシをご覧ください。
【自主研修のススメ シリーズ】
・公開講義の事後配信 こちら
・特センに来所して行う研修 こちら
冬季休業中の自主研修などに、ご活用ください。
【R6.12.10(火)更新】
北海道聴覚障害教育研究会(略称「北聴研」)は、道内の特別支援学校(聴覚障がい)の教職員が中心となり、日常の教育実践のより一層の発展、充実を期して設立、運営されている研究会です。主な事業として、聴覚障がい教育の発展と教員の専門性の向上を目指し、研究大会や研修会を開催しています。
令和7年1月9日(木)に、「令和6年北海道聴覚障害教育研究会 冬季研修会」を開催します。
講師:山形県立山形聾学校長 庄 司 美千代 氏
(元文部科学省初等中等教育局特別支援教育課調査官)
演題:聴覚障がい教育における主体的・対話的で深い学びの実現に向けて
方法:オンライン配信
参加申込締切は、令和6年12月16日(月)です。
詳しくは、こちらの開催要項をご覧ください。
〇 北聴研のホームページはこちら
【R6.12.9(月)更新】
東京大学先端科学技術研究センターは、北海道教育委員会の協力を得て、魔法のキャラバンin北海道『学びの壁を越えるために〜読み書きや学校生活の困難をサポートするためのICT機器活用講演会・機器体験会〜』を開催します。
子どもの学びにICT機器を活用することを通して、家庭や教育現場で役立つ具体的なアイデアや考え方、最新情報を学べる場となっています。
詳細は、次のとおりです。
開催日:2025年1月10日(金)
午前:親子・支援者向けプログラム
午後:教員向けプログラム
場 所:北海道札幌視覚支援学校(札幌市中央区南14条西12丁目1番1号)
*会場には、公共交通機関にてお越しください。
費 用:無料
そのほか、プログラムの詳細や申込みは、次のWebページからお願いします。
【R6.12.5(木)更新】
新篠津高等養護学校は、北海道教育委員会事業として地域連携研修会を開催します。
本研修は、会場参加またはZoomによるオンライン参加を選択するハイブリッド形式です。
・演題 「知的障がい教育における主体的・対話的で深い学びからの授業づくり」
~シン・実践作業学習 A to Z~
・講師 植草学園大学准教授 髙 瀨 浩 司 氏
詳細や申込みについては、次の御案内、リーフレット、参加申込用紙をご覧ください。
〇 御案内
〇 リーフレット
〇 参加申込書
【R6.12.4(水)更新】
特センでは、障がいのある幼児児童生徒を理解し指導に生かすため、心理検査の実施と活用に関する基礎的な知識や技能を身に付ける「心理アセスメントコース」を、次のとおり開催します。
<事前研修>
夏季の実施した際に収録した北海道教育大学函館校の 青 山 眞 二 特任教授の基調講義「アセスメントの意義と心理検査の活用」を視聴します。
<本研修>
各部会に分かれて、演習を通して心理検査の正しい実施方法を学んだり、検査結果を読み取り、指導に生かす方法を検討したりします。
受付終了 1月14日(火)部会1:WISC-V知能検査 部会2:田中ビネー知能検査V
受付中 1月15日(水)部会3:KABC-Ⅱ 部会4:テストバッテリー(鈴木ビネー、PVT-R、S-M社会生活能力検査)
*夏季の実施と異なり、一日での実施に変更するとともに、お申込みは、一人一部会のみとなります。
申込期間は11月19日(火)~12月24日(火)までですので、下記のWebページの「申込み」からお申し込みください。
重要【研修形態・日程・内容の変更について】
*心理検査用具の機密を守る観点...
【R6.12.3(火)更新】
特センに来所し、特別支援教育に関わる専門書や関連資料の閲覧のほか、心理検査用具を活用した個人演習など、自らの課題に応じて研修を行うことができます。
主に図書室を利用して、自主的な研修に活用いただいており、希望に応じて所員から助言や情報提供を行うこともできます。
冬季休業中など、是非ご利用ください。
申込みは、こちらのWebページをご覧ください。
※来所を希望される一週間前までに、お申込みください。
【R6.12.2(月)更新】
道教委は、ICTに関する情報を集めた広報誌「GIGAワールド通信」第44号を発行しました。
今号では、授業の質の向上や校務の効率化に向け、学校DX戦略アドバイザーの講演概要やデータの保全管理、生成AIの利活用等について紹介しています。
11月13日(水)に実施した「管理職向け研修」の報告も掲載しています。
なお、12月18日(水)に予定している「ICT活用全道協議会」の案内は、43号をご覧ください。
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R6.11. 29(金)更新】
特センでは、特別支援教育の理解啓発を図ることを目的に、公開講義の事後配信を実施します。
冬季休業中の自主的な研修等にお役立てください。
また、配信期間は令和6年12月20日(金)~令和7年2月7日(金)までとなっております。
なお、公開する研修動画は次のとおりです。
※動画は120分程度です
①「アセスメントの意義と心理検査の活用」
北海道教育大学函館校特任教授 青 山 眞 二 氏
②「特別支援教育コーディネーターに求められるファシリテーションの力」
北海道教育大学釧路校准教授 田 中 雅 子 氏
③「資質・能力の育成を目指した授業づくり」
国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官 福 本 徹 氏
④「自立活動の指導の基本と実態把握に基づく個に応じた指導の実際」
福岡教育大学教育学部教授 一 木 薫 氏
※本研修動画は教職員等の教育関係者のみを対象に、動画の視聴と講義資料の閲覧ができるようにしております。
詳細は各学校等へ送付した事務連絡とチラシをご覧ください。
【R6.11.27(水)更新】
小樽高等支援学校では、「公開研究協議会兼冬期研修会」を開催します。
協議会(公開授業)や講演(冬季研修会)が行われます。
・演題 だれもが行きたくなる学校づくり -明日から使える生徒指導のコツ-
・講師 神戸親和大学教育学部教育学科教授 金 山 健 一 氏
詳細や申込みについては、開催要項、チラシ等をご覧ください。
〇 開催要項
〇 研修案内ちらし
〇 学校ホームページ
【R6.11.26(火)更新】
道教委では、本道の児童生徒の学力向上や特別支援教育の充実に向け、公立の小学校等に勤務する教員が、道内の研修機関等において長期間集中して研修する機会を設け、確かな指導理論や優れた実践力・応用力を備え、地域や学校における指導的な役割を果たす教員の養成を図る取組を行っています。
今年度、特センでは、石狩市立花川小学校の赤塚 邦彦教諭が長期研修者として研修を行っています。
赤塚教諭は、「特別な教育的支援が必要な児童を二次支援につなげるための初期対応に関する一考察」を研究テーマに設定し、コーディネーターが通常の学級の担任とどのように連携し、実態把握の共通理解を図るかを視点に、調査研究を進めています。
これまで、先行して取り組まれてきた実践や研究等の情報を収集し、児童の実態把握について、「特別支援教育コーディネーターと学級担任の意識に温度差があるのではないか」という仮説を立て、特別支援教育コーディネーター歴が5年以上の教員を対象にインタビュー調査を実施し、結果の分析や仮説の検証に取り組んでいます。
年明けには報告書にまとめるとともに、来年2月には研究成果報...
【R6.11.25(月)更新】
国立特別支援教育総合研究所では、令和3年度から4年度にかけて障害種別特定研究「知的障害教育における授業づくりと学習評価に関する研究」を行い、これまでの知的障害教育で行われてきた一人一人の児童生徒の実態に応じた学習活動についての実践の知見を生かしながら、現在課題とされている学習指導要領の目標・内容を踏まえた単元作成と学習評価に関する研究を行いました。
本セミナーは、知的障害教育における学習評価をテーマとして、実践で参考となる知見を紹介することを目的に開催します。
セミナーの開催について詳しくは、こちらからご覧ください。
また、知的障害教育に関連する研究については、こちらからご覧ください。
【R6.11.22(金)更新】
国立特別支援教育総合研究所では、「インクルDB(インクルーシブ教育システム構築支援データベース)」を運用しています。
インクルDBの「実践事例データベース」では、590件の実践事例を公開しており、子供の実態から、どのような基礎的環境整備や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を掲載しています。
インクルDBについて理解を深め、合理的配慮や基礎的環境整備に関する幼児児童生徒の事例を検索したり、学校や地域での研修等に活用したりできるようになることを目的としたオンラインセミナーを開催します。
〇 セミナーの詳細は、こちらからご覧ください。
〇 インクルDBは、こちらからご覧ください。
【R6.11.20(水)更新】
令和6年(2024年)10月7日(月)に令和6年度(2024年度)運営懇談会を開催しました。 運営懇談会の議事録及び配付資料は次のとおりです。
議事録
配付資料
【R6.11.20(水)更新】
特センでは、公式Instagramの開設に当たり、親しみをもってもらえるよう、新たなキャラクターを作成しました。
公式Instagram及び公式X上で投票を受け付けた結果、キャラクター名が決定しましたので発表します。
本キャラクターの名称は「さぽまる」に決定しました!
(サポートの「さぽ」と、特センがある円山の「まる」が名前の由来です。)
投票へのご協力、ありがとうございました。
特セン公式Instagramについても、フォローやいいね!をお願いします。
今後も、特別支援教育の最新情報を発信していきますので、これからのさぽまるの活躍にご期待ください。
【R6.11.19(火)更新】
特センでは、通常の学級における特別な教育的支援が必要な児童生徒の指導や支援に必要な知識・技能を身に付けることを目的とした研修「通常の学級コース」を開催します。
本日の16時より申込みを受付を開始します。
1月9日(木)に実施する本研修では、教員を講師として、「特別な教育的支援が必要な児童生徒の指導の実際」をテーマに、小学校又は中学校の通常の学級における特別な教育的支援が必要な児童生徒への分かりやすい授業づくりや学級経営を工夫などについて、講義をしていただきます。
また、学級全ての児童生徒に分かりやすい指導を行うための方策について、協議を行います。
申込期間は12月23日(月)までですので、下記のWebページの「申込み」からお申し込みください。
◯ 遠隔研修3「通常の学級コース」のWebページはこちら
◯ チラシ
【R6.11.18(月)更新】
北海道教育委員会は、本道の特別支援教育に関する状況をまとめた「要覧 特別支援教育 令和6年度版」を発行しました。
この要覧には、本道の特別支援教育の充実に向けた取組や特別支援学級の学級数・児童生徒数、特別支援学校の学校数・幼児児童生徒数などが掲載されています。
<掲載内容>
・北海道総合教育大綱、北海道の特別支援教育
・特別支援教育総合推進事業、特別支援教育の充実に向けた事業
・各種データ(特別支援学級の学級数・児童生徒数、特別支援学校の学校数及び幼児児童生徒数、推移など)
・特別支援学校所在地等並びに特別支援学校児童生徒数等一覧
・特別支援教育関係資料
詳しくは、こちらのWebページをご覧ください。
【R6.11.18(月)更新】
特センでは、障がいのある幼児児童生徒を理解し指導に生かすため、心理検査の実施と活用に関する基礎的な知識や技能を身に付ける「心理アセスメントコース」を、次のとおり開催します。
<事前研修>
夏季の実施した際に収録した北海道教育大学函館校の 青 山 眞 二 特任教授の基調講義「アセスメントの意義と心理検査の活用」を視聴します。
<本研修>
各部会に分かれて、演習を通して心理検査の正しい実施方法を学んだり、検査結果を読み取り、指導に生かす方法を検討したりします。
1月14日(火)部会1:WISC-V知能検査 部会2:田中ビネー知能検査V
1月15日(水)部会3:KABC-Ⅱ 部会4:テストバッテリー(鈴木ビネー、PVT-R、S-M社会生活能力検査)
*夏季の実施と異なり、一日での実施に変更するとともに、お申込みは、一人一部会のみとなります。
申込期間は11月19日(火)~12月24日(火)までですので、下記のWebページの「申込み」からお申し込みください。
重要【研修形態・日程・内容の変更について】
*心理検査用具の機密を守る観点から、研修形態・日...
【R6.11.14(木)更新】
北海道肢体不自由教育研究協議会(略称「北肢研」)は、道内の特別支援学校(肢体不自由)の教職員が中心となり、日常の教育実践のより一層の発展、充実を期して設立、運営されている研究会であり、主な事業として、肢体不自由教育の発展と教員の専門性の向上を目指し、研究大会を開催しています。
令和7年1月17日(金)に、参集とオンラインのハイブリッドで「第61回 北海道肢体不自由教育研究大会 拓北大会」を開催します。
公開授業やポスター発表のほか、文部科学省の菅野視学官による講演が行われ、オンラインによる試聴が可能です。
参加申込締切は、令和6年12月6日(金)です。
詳しくは、こちらの二次案内をご覧ください。
【R6.11.13(水)更新】
特センでは、実習助手の役割について理解を深め、生徒の取組を充実させるため、実習担当の教諭と連携し、作業学習及び実習方法等の工夫・改善に努めながら、実習助手として資質能力の向上を図るための知識・技能等を身に付けることを目的とした研修「実習助手コース」を開催します。
現在、申込みを受付中です。
1月10日(金)に実施する本研修では、特別支援学校実習助手による「実習助手の業務の実際」についての講義を通して、作業学習等の工夫や教職員間の連携のポイントについて学びます。
また、自校の強みを再認識したり、他校の特色ある取組を知ったりする交流・協議を行います。
申込期間は12月20日(金)までですので、下記のWebページの「申込み」からお申し込みください。
◯ ハイフレックス研修6「実習助手コース」のWebページはこちら
◯ チラシは、こちらからご覧ください。
【R6.11.12(火)更新】
北海道特別支援学校長会道南支部は、「本人の自立に向けた進路指導ガイドブック」を作成しました。
本ガイドブックでは、各学校等において、卒業時の進路をどう選択するかだけではなく、どのように働き、どのように暮らしていくかという長期的展望に立って進路指導を行うことができるよう、義務教育終了後の進学先や卒業後の働き方、暮らし方を紹介しています。
詳しくは、下記のリンクからダウンロードしてご覧ください。
〇 本人の自立に向けた進路指導ガイドブック
〇 本人の自立に向けた支援会議シート
【R6.11.11(月)更新】
NISEでは、小・中学校等で初めて特別支援学級や通級による指導を担当する先生、特別支援教育に学ぶ機会がなかなか得られなかった先生に向けて、障がいのある児童生徒がそれぞれの学びの場でより良く学び、充実した学校生活を送れるようになるためには、どのように取り組んでいくと良いか考えていくためのきっかけとなる内容をまとめ、取組のヒントとなる情報を記載した「特別支援教育リーフ」を作成しています。
次のとおり、最新号が発行されましたので、ご紹介します。
Vol.20 知的障害のある児童生徒の学びを支える各教科について
Vol.21 知的障害のある児童生徒の学びを支える学習評価について
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
{{item.Topic.display_summary}}
6
0
7
9
5
5
8
要覧
特別支援教育教育課程改善の手引
特別支援教育教育課程改善の手引はこちらから
公式SNS等
◯ プライバシーポリシー
特センについて
◯ 住 所
北海道札幌市中央区
円山西町2丁目1番1号
◯ 電話番号
(教育相談)011-612-5030
(代 表)011-612-6211
◯ 代表メールアドレス
tokukyo.12◆pref.hokkaido.lg.jp
※◆に@を入れてください。
◯ 教育相談メールアドレス
tokucensoudan◆hokkaido-c.ed.jp
※◆に@を入れてください。